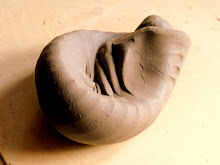ここひと月ほど、塗装の研究に没頭している。
柱や梁などは、使い慣れ、風合いも気に入っている「関西ペイント」のオイルステインで仕上げたが、床や腰壁、天井等、板材で面積の大きい場所は、自然系の水性塗料で仕上げようと決めていた。
ところが、いざ使ってみると上手く行かないのだ。
色も風合いも気に入らず、何より数倍手間が掛かる。
塗装は子供の頃から親しんで居り自信があったのだが、水性は初めてだ。
詳しい友人等も居るのだが、聞いてしまえばそれで終わりである。
自分で解らなければ身にならないので、色々取り寄せ試験を繰り返している。
静岡の「大橋塗料」さんから取り寄せた、ワンダー水性1液型、ワンダーステイン(キャピタルペイント)。ドイツの自然塗料メーカー、リボス社の蜜蝋ワックス「グレイボ」等。
リボス・カルデット(植物性オイル塗料)、サンプル。
他色の塗り重ねや、顔料(ワンダーステイン)の添加等で好みの色を探す。
「グレイボ」を塗り磨くと自然な艶が出る。
古色の茶系とは別に、もう一つ出したい黒みがかった色がなかなか出なかったが、ふと思いつき墨(墨汁)を混ぜてみたら決まった。
これは水性の利点であろう、墨汁が混ざるのだ。
塗料の着色材は、金属の微粒子が主だと思う(たぶん)。墨も炭素の微粒子で褪色の心配もない。
赤みを出したければ、弁柄の添加も良いだろう。
塗装も深い!